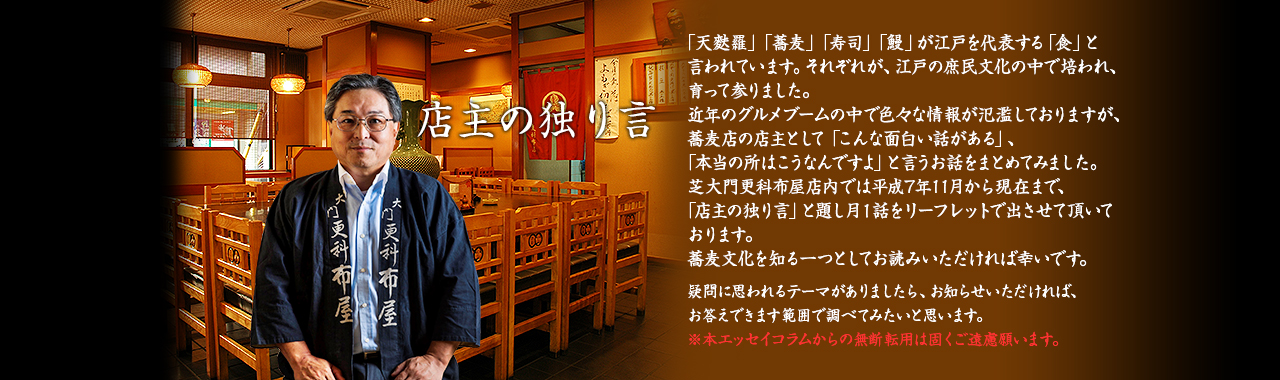2025年10月 第193話 大食い選手権
初物に対する行動は江戸っ子らしさを表すものですが、一昔前に数々のTV番組となった大食い選手権も江戸の食文化の一風景でした。蕎麦の大食いと言えば「わんこそば」がすぐ頭に浮かびますが、あれは一杯が誠に少量。江戸の選手権には記録では中平盛りとありますから当店のモリせいろ並みの量と考えられる二八蕎麦がその基準であったようである。さてこの大食い選手権もしっかりと舞台が設定されていて会場として名を馳せたのが浮世絵にも度々登場の両国柳橋の「万八楼」なる料亭であったそうだ。
ここを会場にした中でもつとに有名なのが文化14年(1817)の大食会で、多くの書物に記録が残されていました。
この大会の種目は5部門「飯」「蕎麦」「鰻」「菓子」「酒」で競われ、参加者は150人で結果は「飯組」第1位は味噌と香の物に醤油2合で茶漬碗68杯を平らげた三河島の三右衛門41歳。「菓子組」は好きな物を組合せて食べたようで神田の丸屋勘右衛門56歳が饅頭50個、羊羹7棹、薄皮餅30個、お茶19杯で優勝。「蕎麦組」は冒頭で紹介した大きさのせいろで平盛り何と63枚を平らげた八丁堀の吉兵衛38歳。「鰻組」は優勝者の記述は無かったが、代金にして1両2分(現在に置き換えると約22万5000円分)の記録で、1枚1500円に換算すると150枚を食したことになる。「酒組」ご当地芝の鯉屋利兵衛30歳が3升盃で6杯半(約35?)を飲んだとされている。
天保2年(1831)の大会では162人が参加、予選通過ラインの飯15杯をクリアー後に天ぷら340個や油揚げ150枚、梅干600個や蜜柑505個、醤油1升8合、塩3合といった凄まじい記録が書かれています。大酒大会はさらに凄まじく個人戦からチーム戦まで大勢の酒豪が競い合ったそうだ。中でも慶安元年(1648)の川崎大師での2組のチーム戦と文化12年(1815)の千住の個人戦が記録に残る大会となっている。前者は15人対15人で鎌倉盃と言われる7合の大盃の一人1杯の回し飲みリーレー、後者は短時間での一気飲み競技で7升5合が最高記録となっている。数字だけ見て全てを鵜呑みには出来ませんが、とんでもない量を次々に平らげて見せる大食漢や大酒飲みによる選手権は初物ブームと同じく泰平の世ならではの庶民町人の贅沢な遊びであり、虚実取り混ぜて江戸で大人気となったのでしょう。しかし全国的な凶作による大飢饉で始まった天保の改革以後すっかり姿を消したと言うことである。